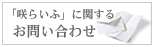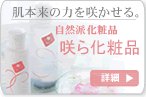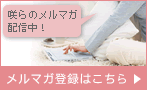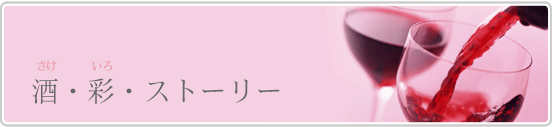
���E�ʁE�X�g�[���[
 |
 |
|
 |
|
|
|
|

�V�����p�[�j�����͂��߂Ƃ��锭�A���̃��C���́A�Ȃ��A�ݏo���̂ł��傤���B
�����̖A�̐��̂́A�����ł���u�h�E�y�����邱�Ƃɂ���Đ������_���Y�f�ł��B�u�h�E�Ɋ܂܂�Ă��铜���͍y��ہi�r�[����p�������Ƃ��ɂ��o�ꂵ�܂��I
���̍y��̒��ł����C����p�̍y��ۂ��g���܂��B�j�̍�p�ɂ���āA�A���R�[���Ɠ�_���Y�f�i���Y�_�K�X�j�ɕς��܂��B
���A�����C���́A���̃A���R�[�����y��
�i�P�j �r�̒��ōs���B�@�@�@�@�@ �i�Q�j ��^�^���N�̒��ōs���B�i���̂��Ƃɕr�ɂ���������B�j
���@�Ƃ�����܂����A����
�i�R�j���C�����������ɒY�_�K�X�𒍓�����
���@�ō���邱�Ƃ�����܂��B
���{�ň�ʂɁu�V�����p���v�ƌĂ����̂͂��Ƃ��ƃt�����X�́u�V�����p�[�j���n���v�ō��ꂽ���A���̃��C���u�V�����p�[�j���v�ɗR��������́B����͏�̇@�̕����ō���܂��B�u�V�����p�[�j���v�͎g����u�h�E�̎�ނ��͂��߁A�����܂Ō����ȋK�肪����A�܂����Ɏ�Ԃ���������̂Ȃ̂ł��B�@
���āA���̔��y�ɂ���Đ������Y�_�K�X�́A�R���N���܂ł����ƐÂ��ɑ�����߂��܂܁A���̏u�Ԃ�҂��܂��B

 �r�̒��ɕ����߂��Ă���Y�_�K�X�́A���C���̉t���̑��ɂ��r�̒��̋�C�ɂ����݂��Ĉ��͂̃o�����X��ۂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�ЂƂ��ѕr���J����Ƃ��̃o�����X������āA�t���̒Y�_�K�X���A�Ƃ����`�Ő��܂�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�r�̒��ɕ����߂��Ă���Y�_�K�X�́A���C���̉t���̑��ɂ��r�̒��̋�C�ɂ����݂��Ĉ��͂̃o�����X��ۂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�ЂƂ��ѕr���J����Ƃ��̃o�����X������āA�t���̒Y�_�K�X���A�Ƃ����`�Ő��܂�Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
���̃V�����p�[�j�����O���X�ɒ������ƁE�E�E
�ǂ�����A�����܂�Ă���̂ł��傤�E�E�E���́A�A�̔������̓O���X�ɕt�����������������@�ۂ̂悤�ł��B�V�����p�[�j�����O���X�ɒ����ł����̑@�ۂ̂����Ŋ��S�ɂ̓O���X���G��邱�Ƃ͂���܂���B�����ɒY�_�K�X�����荞�݁A��������͂��Ȃ����������A�̈ꐶ���n�܂�܂��B
�͂��߂̓O���X�ɋz�����Ă��܂����A���̂������g�̕��͂ɂ��O���X���痣��A�㏸���Ă����܂��B�㏸���Ȃ���A�t���̍���̐�����Y�_�K�X�����̑̂ɒ~���Ȃ��琬�����đ傫���Ȃ��Ă����܂��B
�A�̑傫�����傫���Ȃ�قljt��������R�͑傫���Ȃ�܂��B��������Ə��X�ɏ㏸�X�s�[�h�͗}�����Ă����̂ł��B���Ƃ��ƃV�����p�[�j���̉t���ɗn���Ă���Y�_�K�X�̗ʂ̓r�[���̂���Ɣ�ׂĖ�3�{�������B����傫���A�����Ă������Ɖt�ʂɂނ����Ă����܂��B
�₪�ĖA�͎��g�̕���ƂƂ��ɂ��̒Z���ꐶ���I���܂��B�e������̉t�ʂ͈�U���݂����܂����A�����Ɉ�̞��̂悤�ȉt�ʂ̏㏸���ł��܂��B��������̏u�ԁA�ׂ��Ȃ������ɕ������āA�t�ʂɌ������Ȃ���~���Ă�������̐������ꏏ�ɋ�C���ɕ��̂ł��B�A�͖����̗���Ȃ��ď㏸���Ă��Ă��܂�����A���ꂪ�����玟�ւƁE�E�E�������Ď������͂��̖��f�I�ȍ���ɏo��̂ł��B

���̖A�̈ꐶ���ώ@����ɂ͍ג����t���[�g�^�ƌĂ��O���X�̌`���K���Ă���ł��傤�B���̕������������߁A�A�ƂƂ��ɕ����ꂽ����̐��������̕������L�����̂����Ïk����Ă�苭�������邱�Ƃ��ł��܂��B

 �������A���̂܂܂ł��\���ɔ�����������������̂ł����A�t���[�c���g�����V�����p���J�N�e���͂������ł��傤���B
�������A���̂܂܂ł��\���ɔ�����������������̂ł����A�t���[�c���g�����V�����p���J�N�e���͂������ł��傤���B
���̎����̓u�h�E���������߂ł��B
�u�h�E���T�`�U���A��Ǝ����菜������A���ʂ̃V�����p�[�j���i���A���̃��C���ł������������܂��j�𒍂��A���̒��Ōy���ׂ��܂��B
�������������g���ĕs�����Ȃǂ���菜���A�ׂ����u�h�E�ƂƂ��ɃO���X�ɓ���āA�D�݂̗ʂ܂ŃV�����p�[�j���𒍂��ł�������B
�t���[�c�̓u�h�E�łȂ��Ă��{�̂��̂�OK�B
�t���[�c���V�����p�[�j���̒��Œׂ����Ƃɂ���ăt���[�c�ƃV�����p�[�j�������݂��Ȃ��݂܂����A�t���[�c���O���X�̒�ɒ��܂Ȃ��J�N�e�����ł��܂��B�V�����p�[�j���̍���ƂƂ��Ƀt���b�V���ȃt���[�c�̍�����y���߂܂��B
![]()
�����̂������낢�Ƃ���́A���ꂽ���������H����ĈႤ�`�ő��݂������邱�ƁB
�r�̓^�C���J�v�Z���̂悤�Ȃ��̂ł��B�V�����p�[�j���̖A�����͂Ƃ����t�����X�̃V�����p�[�j���n���̃u�h�E�B�����̕��̎���o�āA���ԂƎ�ԂЂ܂������Ĉ�Ă��Ă��܂����B���́A���̋Ïk���ꂽ���Ԃ�A�̐����Ƃ����`�ŃO���X�̒��Ō����Ă���Ă���悤�Ɏv���̂ł��B
�V�����p�[�j�����y���ނƂ��́A���̎��ԂɎv�����͂��Ȃ��珢���オ���Ă݂Ă͂������ł��傤���B
�i�Q�l�����F���o�T�C�G���X�@2003�N3�����j
![]()